2020.04.15
遺言の重要性③【内縁の法律関係】
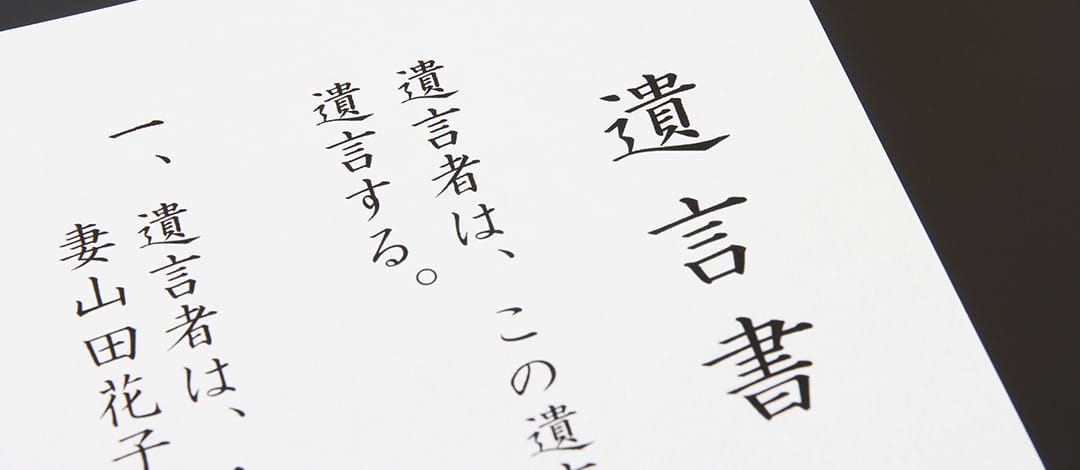
今回は、内縁関係にある人には遺言が絶対に必要だ、ということを、ケースを通じて解説したいと思います。
【ケース ③】
Aさんは、Bさんと、Aさん名義の家に住んでいました。AさんとBさんは婚姻関係にはなく、内縁関係を継続したまま、30年以上同居していたのです。
Aさんには、子がいませんでした。
Aさんは、内縁の場合には遺言を作らなければならない、と、なんとなく聞いてはいたものの、「ちゃんとした内容の遺言の作り方はわからないし 」と、なんとなく作らないままでいましたが、ある日、突然亡くなってしまいました。
Bさんは、Aさんとの思い出が詰まった家に住み続け、余生を過ごそうと考えました。
ところが、Bさんのもとに、突然、Aさんのきょうだいだと主張するCさんから連絡があり、Aさんの家は自分が相続するので出ていってくださいと言われてしまいました。
Bさんは、Aさんにきょうだいがいることなど聞かされておらず、Cさんのことなど全く知りません。でも、戸籍を確認してみたら、Cさんは、本当にAさんのきょうだいだったのです。
Bさんは、家を出ていかなければならないのでしょうか。

【解説】
内縁関係にあるだけでは、相続に関する権利は得られません。なので、このケースのようなことは全く不思議ではありません。Cさんは酷いと思われる方もいるかもしれませんが、Cさんにしてみれば、当然の権利を行使しているだけだったりします。
もっとも、全く救いがないわけではなく、このケースでは、Bさんは、Cさんからの明渡請求に対し、権利の濫用だと主張し、居住を続けるべく争うことが考えられはします。実際に、そのような主張を認めた裁判例もあります。
しかし、同様の判断が出るかどうかについては、状況次第というところもあって、100パーセント安心とは言い切れませんし、そもそも、裁判所にそのような判断をしてもらうには、大変な労力をかけて争う必要があります。
ところが、このケースでは、Aさんが、ちゃんとした対策、たとえば、「すべての財産をBに相続させる。」等記載した遺言を作成してさえいれば、Bさんは、そんな大変な目にもあうことなく、確実に家に住み続けることができました。相続人がきょうだいだけの場合、そのきょうだいには遺留分の権利はないので、Aさんの作った遺言に対して、基本的には、とやかく言う権利もないためです。
今回覚えてほしいことは、内縁関係にある場合には、何らかの対策が必須だということに尽きます。
その場合、対策としては遺言作成でいいのか、遺言作成を採用したとして、どのような内容にするのがいいのか、など、ご相談いただければ、その方に応じたアドバイスができるかと思います。何をしたらいいかわからない、と思っているのであれば、一度ご相談ください。
なお、内縁関係については、また、別に詳しくご説明しようと思います。

